魏志倭人伝や後漢書などに出てくる「大夫」という身分。
大夫は、中国の王朝に朝貢した倭国からの使者を指していると言われています。
この大夫、どのくらいの頻度で朝貢していたのでしょうか?
『礼記』という史料から推測してみました。
朝貢頻度の謎
大夫の話の前に、朝貢について簡単に整理してみます。
朝貢とは、諸外国の君主が中国皇帝の徳を慕い、貢物を持って中国に来ることを指します。
ちなみに、朝貢の見返りに中国皇帝が回賜を与え国王に任命することを「冊封」と呼びます。
『漢書』には、倭人が朝貢していたとする記述があります。
その朝貢頻度は”歳時”となっています。
「楽浪海中有倭人、分為百餘國、以歳時來献見云。」
超簡易訳:楽浪郡の海の向こうには倭人が存在し、百余りの国に分かれており、歳時に貢物を献上していたと言う。
『漢書』巻28『地理志』「燕地条」
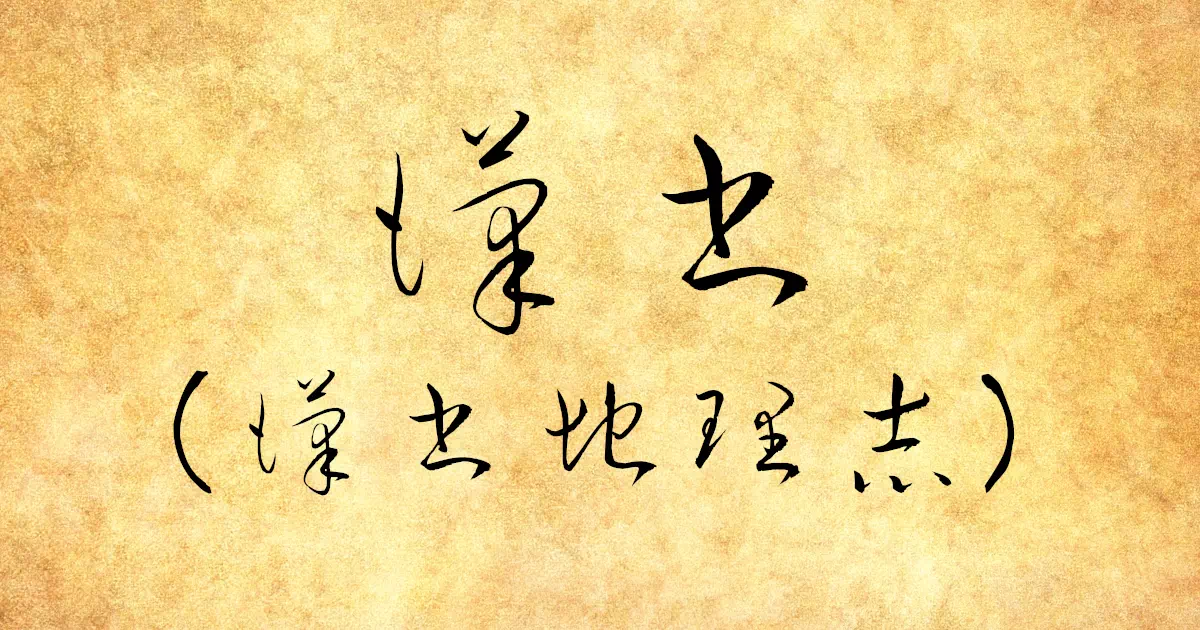
一般的に「歳時」とは一年のこと、あるいは季節ごとという意味で使用されます。
一方で、当時の航海術・移動手段や距離を考えると、1年ごとや季節ごとに頻繁に行き来することは現実的ではないと考える説もあります。
よってこの漢書の記述は、定期的あるいは事あるごと(王が代わった時など)と解釈されることがあります。
『漢書』から倭からの使者の朝貢頻度は”歳時”だったことが分かります。
この”歳時”の解釈は、一年、季節ごと、定期的、事あるごと、などの説があります。
大夫という身分は何か
ここからが本題ですが、大夫とは何でしょうか?
『礼記』王制篇での大夫
大夫とは何かを知るために、『礼記』の王制篇の記述を見てみましょう。
原文「諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝」
鄭玄の注釈「比年每歲也小聘使大夫大聘使卿朝則君自行然此大聘與朝晉文霸時所制也」
超簡易訳:
『礼記』「王制」(附釋音禮記注疏卷第11)
原文:諸侯は天子の元に、毎年小聘を、3年ごとに大聘を派遣し、5年ごとに諸侯自らが朝貢する。
鄭玄の注釈:比年とは毎年のこと。小聘は大夫を、大聘は卿を使わすことである。(以下省略)
原文を読む@漢籍電子文献資料庫(新漢籍全文)
2024.01.13 閲覧確認
「免費使用」をクリックし、【全庫瀏覽】 から經 → 十三經 → 重刋宋本十三經注疏附校勘記 → 重栞宋本禮記注疏附校勘記 と進み225-1へ。
『礼記』の王制篇は、前漢時代の王の政治制度を記述したものです。
また、ここで言う諸侯とは、中国王から与えられた封土内で”君”を名乗ることができた者を指します。
つまり諸侯は中国国内の一部を収める首長であり、5年に1回朝貢したということになります。
さらに諸侯は、部下の卿を3年に1回、大夫を毎年朝貢させていたようです。
倭における大夫
後漢書や魏志倭人伝では、倭の使節は「大夫」を自称していたとしています。
「建武中元二年倭奴国奉貢朝賀使人自稱大夫」
『後漢書』巻85「東夷列伝」
「景初二年六月倭女王遣大夫難升米等詣郡求詣天子朝献」
『三国志』巻30『魏志』「烏丸鮮卑東夷伝」倭人条
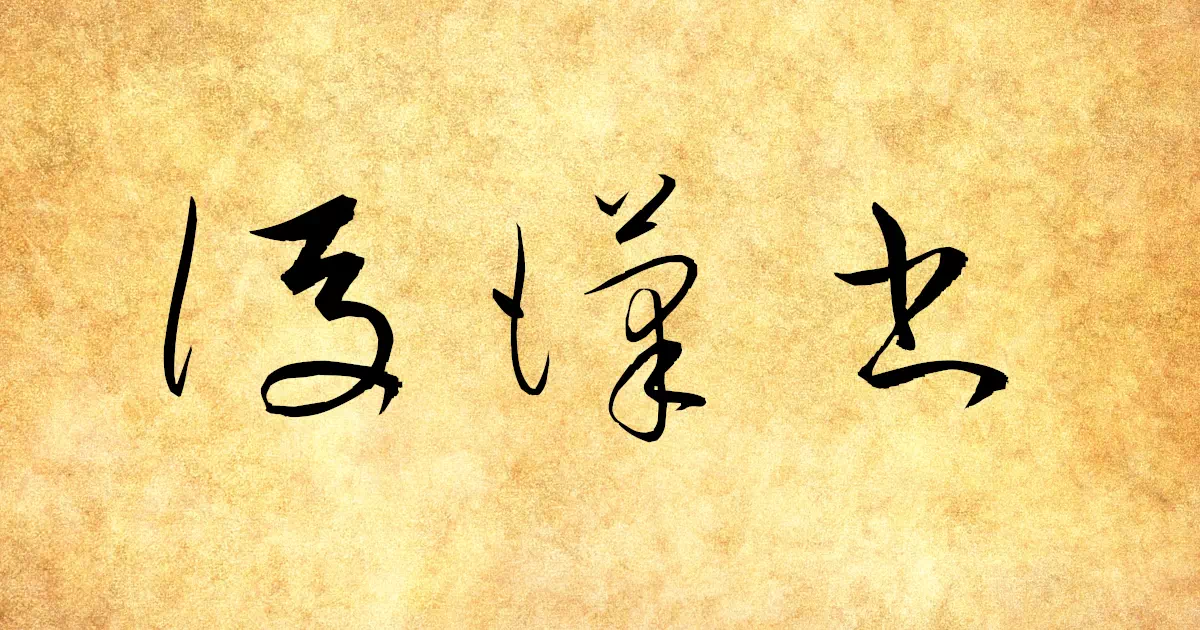
ここで重要なことは、倭人が大夫を自称しているだけであり、中国側が大夫と認めたとは限らない点です。
中国側の「大夫」と日本側の「大夫」は意味が違う可能性もあります。
倭から大夫が来たと言うことは、倭と中国は対等ではなく中国の一部という認識だったのでしょうか?
倭は中国国内の国ではないものの、倭からの使者は中国国内の大夫に相当する身分と考えることもできます。
大夫とは「中国の王に毎年訪問する、諸侯からの使者」であると推測されます。
大夫の意味は時代によって変わるか
ここで注意すべきととして、大夫という身分が時代によって同じ意味とは限らないという点があります。
まず『礼記』は全49篇ですが、篇によって成立年はバラバラです。
大夫の記述がある王制篇は、前漢の文帝(紀元前180~157年頃)の成立とされています。
しかし、注釈を付けている鄭玄は127~200年頃、時代的には後漢の人物です。
一方で、後漢書に出てくる大夫は建武中元二年(57年)、魏志倭人伝に出てくる大夫は景初二年(238年)に朝貢していることになっています。
| 史料 | 史料成立年代 | 大夫朝貢年代 |
|---|---|---|
| 礼記(原文) | 前漢:文帝の時代(紀元前180~157年頃とされる) | 記述無し |
| 後漢書 | 432~445年頃 | 建武中元二年(57年) |
| 漢書 | 80年頃 | 記述無し |
| 礼記(注釈) | 127~200年頃(← 鄭玄の生没年) | 記述無し |
| 魏志倭人伝 | 280~297年頃 | 景初二年(238年) |
ここで内容を整理してみましょう。
前漢(さらに絞ると紀元前180~157年頃)では、ルール上は毎年大夫が朝貢していたことになります。
その後、後漢(57年頃)や三国時代(魏・238年頃)に倭から朝貢した大夫ですが、その前後の年に朝貢したという記述はありません。
春秋二倍暦説(春夏で1年、秋冬で1年とする数え方)など、倭と中国では”年”の数え方の認識が異なっていた可能性もあります。
朝貢頻度を解明することの重要性
邪馬台国の比定地を論争するにあたって、朝貢頻度が分かることは必須ではありません。
そのため、季節ごと、一年ごと、数年おき、事あるごと…と認識に違いがあっても大きな問題ではないでしょう。
しかし、現在見つかっている倭が朝貢した記録が全てなのか、残っていないだけでもっと交流頻度があったのか、という事実の解明は、邪馬台国が存在した頃の倭の様子を知る上で貴重な情報になり得ます。
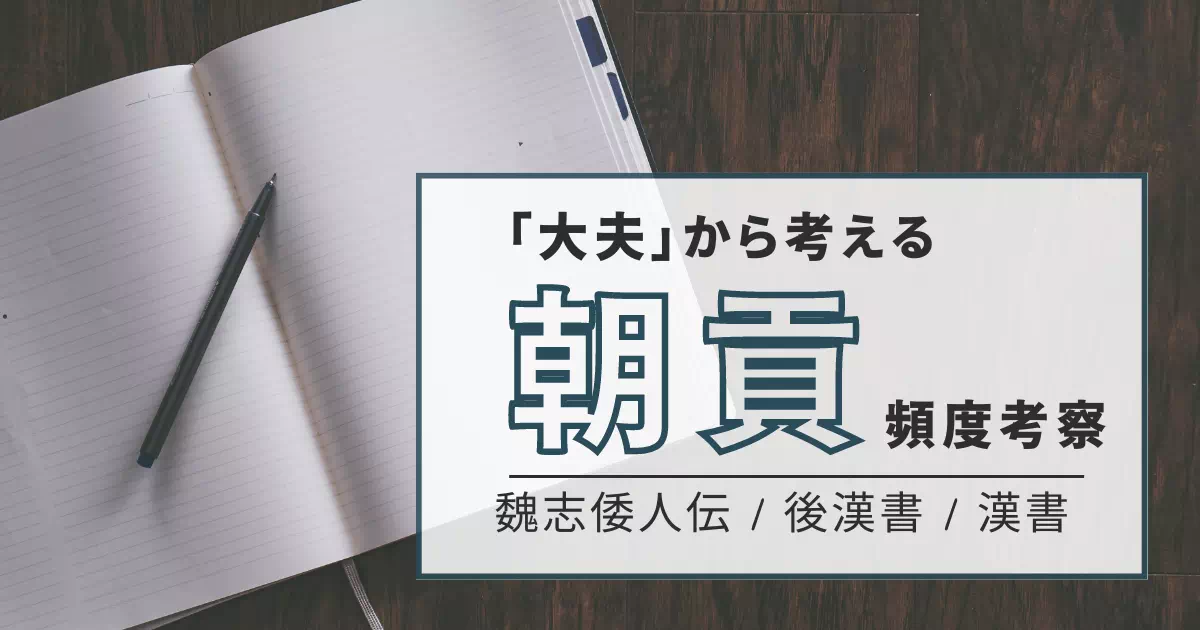
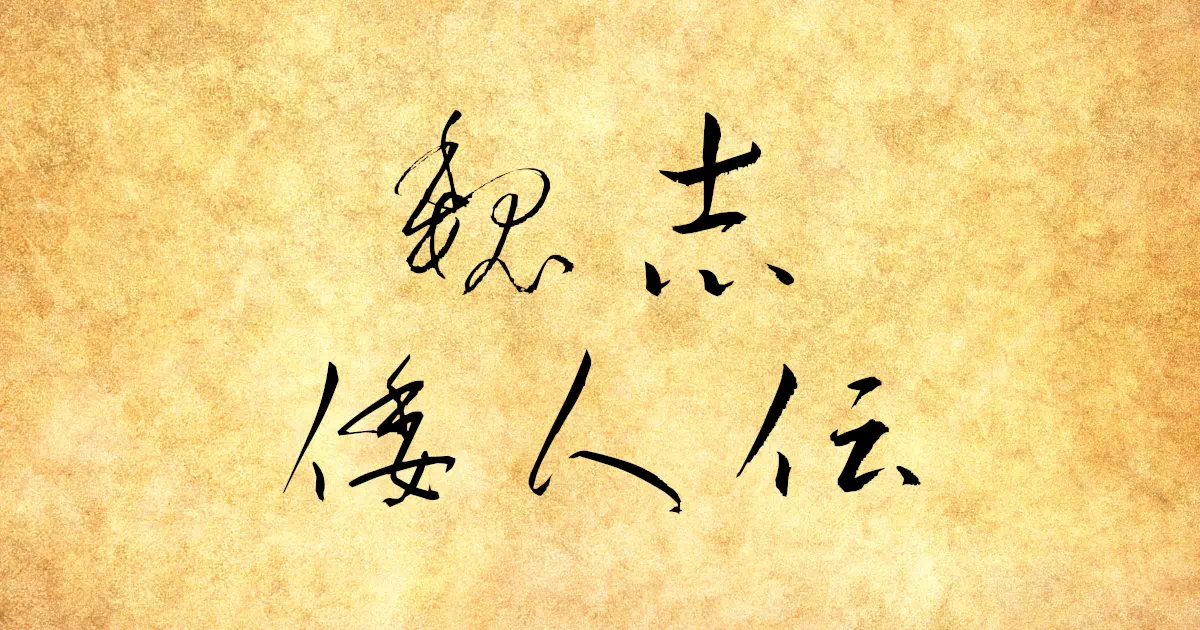
コメント